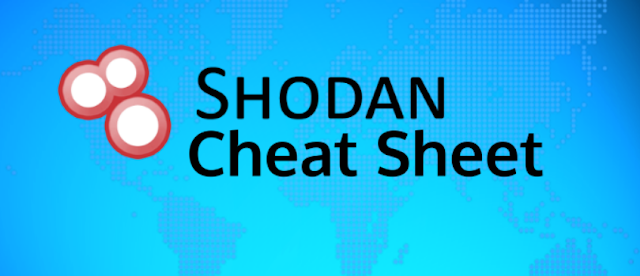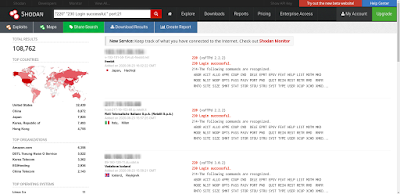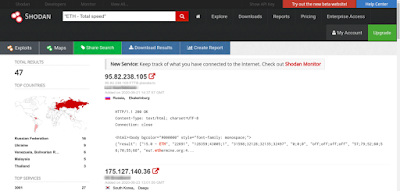セキュリティツールというと、まず思い浮かぶのはスキャンや攻撃を行うツールかもしれません。
実際、Kali Linuxに代表されるような攻撃・調査系ツールは分かりやすく、成果も目に見えやすい存在です。
一方で、実際の現場ではそれだけではセキュリティは回りません。
ログを集め、可視化し、依存関係を把握し、資産の変化に気づき、対応を自動化する。
そうした地味で継続的な作業を支えているツール群が存在します。
今回取り上げるのは、そうした
派手さはないものの、実務では確実に使われているセキュリティツールです。
攻撃を行うための道具ではなく、
「把握する」「管理する」「運用する」ためのツールを中心に選びました。
ツールの新しさや話題性ではなく、
どんな場面で、どんな役割を担うのかに着目して眺めてみると、
セキュリティの見え方は少し変わってくるはずです。
BLint
BLint は、実行ファイル(バイナリ)を対象に、
セキュリティ上の特性や構成を静的にチェックするためのツールです。
ソースコードではなく、ビルド後の成果物そのものを入力として扱う点が特徴で、
スタック保護の有無やハードニング状況などを確認できます。
近年は SBOM(Software Bill of Materials)生成にも対応しており、
ソフトウェアサプライチェーンの文脈でも使われる場面が増えています。
使いどころは派手ではありませんが、
「何が含まれているか分からないバイナリ」を前にしたとき、
最低限の構造やリスク感を把握する用途として有効です。
特に、
-
外部から提供された実行ファイル
-
ビルド環境が完全には把握できていない成果物
を扱う場面では、最初の確認手段として位置づけやすいツールです。
入手先
Cloud Console Cartographer
Cloud Console Cartographer は、
クラウド環境の操作ログを整理し、人が理解しやすい形に変換するためのツールです。
クラウドの管理コンソール操作ログは量が多く、そのままでは
「何が起きたのか」を把握しづらいことが少なくありません。
このツールは、そうしたノイズの多いログを意味のあるイベント単位にまとめることを目的としています。
不正操作の検知やインシデント調査といった場面だけでなく、
「誰が・いつ・どのような操作を行ったのか」を
後から追える形に整える用途でも役立ちます。
SIEMほど重い仕組みを入れる前段として、
クラウド操作の可視化を一段整理したいときに位置づけやすいツールです。
入手先
Encrypted Notepad
Encrypted Notepad は、
保存されるファイルが常に暗号化されるシンプルなテキストエディタです。
編集中の内容を含め、ファイルは AES-256 によって暗号化された状態で保存され、
特別な操作を意識せずとも「平文で残らない」ことが前提になります。
広告表示やネットワーク通信がなく、機能も最小限に絞られています。
セキュリティ設計書のメモや、一時的な認証情報、
調査中に書き留めた断片的な情報など、
残しておくが平文では置きたくないテキストの扱いに向いています。
派手なことはできませんが、
「置き場所に悩む情報」を安全側に寄せるための
個人レベルの現実的な選択肢と言えるツールです。
入手先
Grafana
Grafana は、
メトリクスやログをダッシュボードとして可視化するためのツールです。
数値やログをそのまま眺めるのではなく、
グラフや表として並べることで、
変化や異常に気づきやすくすることを目的としています。
単体で完結するというより、各種データソースと接続して使われます。
セキュリティ専用ツールではありませんが、
監視・ログ・アラートといった運用の文脈では、
状況把握の入口として使われることが多い存在です。
「何かがおかしいかもしれない」という感覚を
数値と視覚で裏付けるための土台として、
実務では非常に登場頻度の高いツールです。
入手先
Graylog
Graylog は、
ログを一元的に収集・検索・分析するためのログ管理ツールです。
各サーバーやサービスに散らばったログを集約し、
時間軸や条件で横断的に検索できる点が特徴です。
単なる保管庫ではなく、後から事象を追跡するための基盤として使われます。
インシデント対応やトラブル調査では、
「どのログを見るべきか」が分からないこと自体がボトルネックになりがちですが、
Graylog はその入口を一本化する役割を担います。
派手な検知機能よりも、
あとから事実を確認できる状態を作ることに価値があり、
運用が長くなるほど効いてくるタイプのツールです。
入手先
Mantis
Mantis は、
ドメインを起点にした資産発見や偵察作業を自動化するためのツールです。
サブドメイン探索や証明書情報の収集、
関連ホストの洗い出しといった作業を、
複数の既存ツールと連携しながらまとめて実行します。
単発のスキャンというより、継続的に状況を把握するための仕組みに近い使われ方をします。
ASM(Attack Surface Management)的な発想とも相性がよく、
「何が外に露出しているのか」を
定期的に確認するための前段として位置づけやすいツールです。
手動での偵察に慣れた後、
同じ作業を繰り返すことに疲れてきたタイミングで導入すると、
効果を実感しやすいタイプです。
入手先
OWASP dep-scan
OWASP dep-scan は、
ソフトウェアの依存関係に含まれる脆弱性やライセンスリスクを検出するためのツールです。
アプリケーションやコンテナイメージを対象に、
利用しているライブラリやコンポーネントを洗い出し、
既知の脆弱性情報と突き合わせて確認します。
ソースコードだけでなく、ビルド成果物やイメージを入力にできる点が特徴です。
いわゆる「コードの脆弱性診断」とは異なり、
自分では書いていないコードをどう管理するかに焦点が当たります。
サプライチェーンリスクが意識される場面では、避けて通れない領域です。
CIに組み込んで自動チェックする用途だけでなく、
既存プロジェクトの現状把握にも使いやすいツールです。
入手先
Pktstat
Pktstat は、
ネットワークインターフェースごとの通信量をリアルタイムで把握するための軽量ツールです。
パケットの中身を深く解析するのではなく、
「どの通信が、どれくらい帯域を使っているのか」を
素早く俯瞰することに向いています。
設定や準備をほとんど必要とせず、その場で状況確認ができます。
トラブルシュートや調査中に、
「まず何が通信しているのか」を掴みたい場面で役立ちます。
本格的な解析に入る前の当たりを付ける用途として位置づけやすいツールです。
派手な機能はありませんが、
現場で即使える確認手段として覚えておくと便利です。
入手先
reNgine
reNgine は、
Webアプリケーションを対象とした偵察作業を自動化するためのツールです。
URLやドメインを入力すると、
サブドメイン探索、サービス把握、各種チェックを
あらかじめ定義されたワークフローに沿って実行します。
単発で使うというより、調査の型を固定する用途に向いています。
手作業でのWebリコンに慣れていると、
どうしても抜けや順序のブレが出がちですが、
reNgine はその部分を仕組みとして吸収します。
「自動スキャンで全部終わらせたい」というより、
調査の初動を安定させるための土台として使われるツールです。
入手先
Tracecat
Tracecat は、
セキュリティ対応を自動化するためのOSS SOARツールです。
アラートの受信、情報収集、通知、対応手順の実行といった流れを、
ワークフローとして定義し、自動で回すことを目的としています。
大規模SOC向けの重厚な製品とは異なり、
小〜中規模チームでも扱えることを意識した設計になっています。
人手で行っている定型作業を整理し、
「判断が必要な部分」と「自動化できる部分」を切り分けることで、
対応のばらつきや抜け漏れを減らす用途に向いています。
即効性のある防御ツールではありませんが、
運用が続くほど効いてくるタイプの基盤ツールです。
入手先
まとめ
今回取り上げたツールはいずれも、
一見すると地味で、目立つ成果がすぐに見えるものではありません。
しかし実務の現場では、
把握する・記録する・可視化する・自動化するといった作業こそが、
セキュリティを支える土台になっています。
攻撃手法やスキャン技術が注目されがちですが、
それだけでは継続的な運用は成り立ちません。
今回の10ツールは、
「何が起きているのかを知る」「後から説明できる状態を作る」
という役割を、それぞれ異なる角度から担っています。
ツールの数を増やすこと自体が目的ではなく、
自分の環境や運用に合った道具を選び、使い続けることが重要です。
派手さはなくとも、
こうしたツールがあることで、
セキュリティはようやく“回る”状態になります。